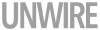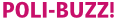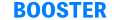『 生き残る種とは
最も強いものでも最も賢いものでもなく
最も変化に適応したものである 』
-ダーウィン進化論-
巨大な生物が地上を支配していた時代にも、終わりは忍び寄っていた。
白亜紀(はくあき)。約1億4400万年前から約6600万年前までの中生代最後の時代。ティラノサウルスなどの大型恐竜が栄えていた時代である。
2025年9月7日、石破茂総理大臣の辞任表明は、戦後日本政治の”白亜紀”終焉のはじまりを告げる瞬間となった。かつて大地を支配した恐竜たちが気候変動という時代の変化に適応できず絶滅への道を歩んだように、これまでこの国を”支配”してきた従来型のオールド政党だけでなく、オールドメディアまでもが民意やデジタルという隕石の衝撃に耐えきれずにいる。
巨大恐竜たちの最後の咆哮
自民党は2025年7月の参院選で39議席という結党以来の歴史的大敗を喫し、公明党と合わせても47議席にとどまった。比例票は前回から約545万票も激減する一方で、参政党や国民民主党といった新興政党が大躍進を遂げた。
この現象は、ティラノサウルス・レックスの巨体が徐々に動きを失っていく様子を彷彿とさせる。体重8トンの巨大な肉体を誇りながら、新たな環境には対応できない——それが今の自民党の姿なのだ。
長寿政権のただの延長線で語られる政治劇、実際の結果と剥離したオールドコメンテーターの予測が優先される選挙報道。「民意」とは、発信者が意図的な層に限定して採ったアンケート結果に都合よく名付けた別名でしかなかったことを誰もが気づき出し、SNSによる情報の民主化で終わりを迎えつつある。
新生代の哺乳類たち
恐竜時代の末期に現れた小さな哺乳類たちが環境変化に柔軟に適応し、やがて地球の新たな覇者となったように、国民民主党が17議席、参政党が14議席と大躍進を遂げた。
国民民主党は前回の2倍を超え762万票で3位となり、参政党は前回から飛躍的躍進で比例票743万票は恐竜たる自民に次ぐ2位となった。両党とも最大野党のはずの立憲をぶち抜いたのだ。かつて大型恐竜の足元をちょろちょろと走り回っていた哺乳類が、いつの間にか森の主役になっていたように、これらの政党は既存の政治生態系に新たな秩序をもたらそうとしている。
両党の躍進の共通点は、『革命的な変革』や『急進的な改革』ではなく、”共感”を重視したアプローチだった。従来のパフォーマンス的対立の枠組みを超えた現実的な政策提案で、既存政治にげんなりしていた有権者の支持を集めた。有権者は雲を掴むような遠距離感の美辞麗句や決意表明などよりも、より近しい『共感できる人間性』や『現実的な解決策』を選んだと見られる。
政界は最早”聖域”などではなく、彼らにも民間と同じレベルを要求していく感覚が成長していくのを感じ取れる。
情報伝達システムの大変革——失われていく「マス」の力
恐竜絶滅の一因とされる「核の冬」は、大気中の塵によって太陽光が遮られ、食物連鎖が崩壊したことにある。現代日本では、テレビや新聞という従来の「太陽」が徐々に力を失い、SNSという新たな光源が台頭している。
かつて新聞の見出しは全国を一斉に動かし、テレビの討論番組は家庭の夕食に入り込んでいた。しかし、スマートフォンが一人ひとりの手に入り、情報が「個の熱量」で動き出した今、中央からの一方通行はもはや急速に力を失いつつある。
参政党の躍進の背景には、YouTubeやX、TikTokといったデジタルプラットフォームを巧みに活用した戦略がある。従来のマスメディアが恐竜の巨大な口から発する咆哮だとすれば、SNSは哺乳類の敏感な聴覚システムのように、細やかで双方向的なコミュニケーションを可能にした。
新世代は、SNSで オールド政権の売国政策やオールドメディアのフィルタリングされた誘導報道の酷さを共有し、専門家の分析により政党の具体性を比較し、YouTubeで議員の素顔を追う。この変化は一過性のトレンドではない。メディアの地層ごと、時代がひっくり返っているのだ。

K-Pg境界の政治学——パラダイムシフトの始まり
地質学者たちが「K-Pg境界」と呼ぶ地層の境界線は、中生代と新生代を分ける決定的な瞬間を示している。現在の日本政治もまた、そのような境界線上にある。
自民党が政権の座にありながら衆参両院で過半数を失うのは1955年の結党以来初めてという事実は、まさに地質学的な断層に匹敵する変化である。この境界を境に、政治システム全体が根本的に変わろうとしている。
選挙特番の視聴率は過去最低、新聞の発行部数も政局記事のPVも目に見えて低下している。現場の記者たちは肌で感じている——「もう”我々の時代”は終わったんだな」と。
適応力という名の武器
恐竜絶滅後の”新生代”は約6600万年前に始まり現在まで続く時代である。
新生代を制したのは巨大さではなく適応力だった。哺乳類たちは体温調節能力、多様な食性、社会性といった特徴を武器に、新しい世界の支配者となった。
現代の政治においても、巨大組織よりも柔軟性と直接性を持つ政党が台頭している。国民民主党の現実的な政策路線、参政党の後援組織をもたないデジタルネイティブな戦略は、まさに新生代型の進化といえる。
いま息づいているのは、まだ小さく、だが凛とした新種の哺乳類たちだ。SNSでしか語らない若手議員、ロゴやグッズを通じて支持者との距離を再構築する新興政党、AIと人間の共創で発信力を飛躍させる市民メディア。どれも既存の型にはまらないが、「届く力」がある。それは声が小さくとも、耳を澄ませば響いてくる”本物の共鳴”だからだ。
絶滅か、進化か
ただし、すべての恐竜が絶滅したわけではない。一部は鳥類として進化し、現在も空を舞っている。同様に、既存政党や既存メディアも、根本的な変革を遂げれば生き残る道があるかもしれない。
テレビや新聞はまるで恐竜のように巨大な骨格を残したまま、俊敏な変化に対応できずにいる。しかし、これは単なる破壊ではない。恐竜が絶滅した後、その遺伝子は鳥類という形で現代まで受け継がれているように、従来メディアのDNAも新しい形で生き続ける可能性がある。
問題は、その変革のスピードが環境変化に追いつくかどうかである。石破退陣後の自民党や古いマスメディアが直面しているのは、「生き残るか、変わるか」という問いなのだ。

新生代日本の黎明
若者という新人類が、この大変革の最大の推進力となっている。彼らは恐竜時代の生き残りではなく、最初から新生代の住民として育った世代だ。テレビの前で受動的に情報を受け取ることよりも、スマートフォンで能動的に情報を収集し、拡散することを自然とする。
政治に触れることは、もはや”野暮な大人の娯楽”ではなくなった。若者が「選ばない自由」から「選ぶ責任」へと向かい始めた。その一票には、もはや”期待”ではなく、”意思”が込められている。
現在の日本政治は、混沌の中から新しい秩序が生まれようとしている過渡期にある。時代は変わった。もう、誰の許可もいらない。”あなたの政治”が、始まっているのだ。
エピローグ——黄昏と夜明けの間で
いま私たちは、歴史の教科書で見た「白亜紀末」と似た空気の中にいる。巨大なものが退場しつつある黄昏。小さな動物が走り出す息吹の夜明け。
石破総理の辞任表明は、巨大恐竜の最後の鳴き声として記憶されるだろう。しかし、その声が消えた後に聞こえてくるのは、新生代の生命たちの活気ある囁きなのだ。
恐竜が滅びたのは「力」がなかったからではない。”隕石”を降らせたのも最早彼らの意志。ならば、次のネイション・デザイナーは誰なのか。その兆しは、各所での旧勢力やカウンター勢力の時代遅れの妨害工作が示す断末魔が響き渡りすでに始まっている。
政治白亜紀の終焉を目撃するあなたは、果たして絶滅する側の恐竜なのか、それとも新時代を拓く哺乳類なのか。答えは、変化への適応能力にかかっている。
・・・数十年を要した政治恐竜の時代は終わろうとしている。
ニュージェネレーションの政治家、メディア、そして有権者たち。
君たちのターンだ。

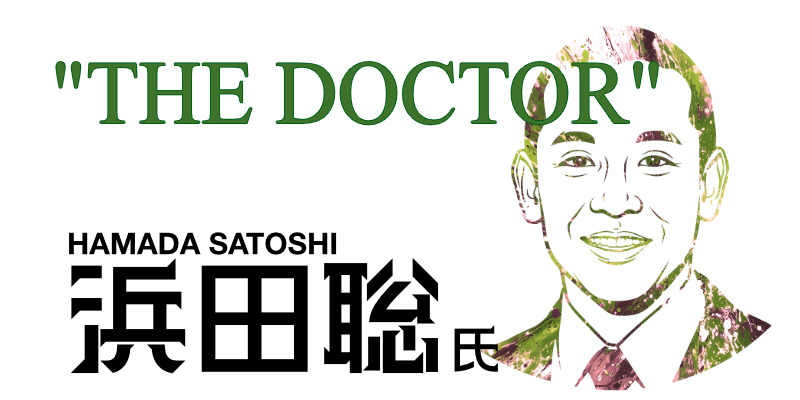
医師から国会へ、常識を問い直す改革者
NHK党の浜田聡さんは 政治家として独自の道を歩んでおり特にNHK問題への取り組みで知られています。
淡々としたキャラクターから想像もつかぬような、刀のような切れ味の国会質問での勇姿や
民意を即座に汲み取りアクションする行動力にギャップ燃え!
メジャー度ではまだまだでも当制作室の 2024年度MVP とも言える議員さんです。
経歴 👨💼
浜田聡さんは 1977年生 京都大学工学部を卒業後、医師になりました。
その後、岡山大学大学院で博士号を取得、医療分野でのキャリアを経て、政治の世界へ転身しました。2019年の参議院選挙で初当選し、任期の6年後である2025年参院選の改選にのぞみましたが33万票(!)も集めながら比例で落選してしまうという結果に、「・・選挙制度ってなんなんだ!?」という問いかけをたくさんの人が首をかしげることになりました。
功績 🏆
1. NHKのスクランブル化の提唱
彼は、NHKを「見ていない人から受信料を徴収するのはおかしい」と考え、視聴者が見たい人だけが受信料を支払うスクランブル化を主張しています。これは、多くの国民が抱えるNHK受信料への不満を代弁するものです。
2. 放送法に関する国会での質疑
国会では、放送法やNHKの運営について積極的に質疑を行っています。受信料のあり方や、公共放送としての役割について、政府やNHKに厳しい質問を投げかけ、問題提起を続けています。
“浜田流”国会質疑BESTセレクション
① 外国からのお金の問題
何が問題?
- 外国の組織が日本の政治に影響を与えようとしている可能性
- NPOやメディアを通じて、こっそり資金が流れているかも
→ 日本の政治が他国に操られる危険性。将来の政策決定が日本人のためじゃなくなる危険性
② 共産党への警戒
- 国の監視機関である公安調査庁が今も監視している共産党は「暴力革命」を完全に否定していないのでは?
→ 保守系政党に数々の妨害工作をする有名団体通称しばき隊などとの関係疑惑も
③ 税金システムの見直し
- 消費税ばかり上げると若者の負担が重すぎる
- 高齢者の再雇用時の税制が複雑
④ NHK改革 📺
- 年間700件近くの不祥事
- 受信料が高すぎる(月額1,300円程度)
- 見たくない人も強制的に払わされる
⑤ 少子化・教育問題 👶📚
- 少子化は国が滅ぶレベルの問題
- 教育費が高すぎて子供を産めない/育てられない
3️⃣ 情報発信による問題提起
SNSやYouTubeなどを活用し、自身の活動やNHK問題に関する情報を積極的に発信しています。これにより、多くの国民にNHK問題への関心を高めるきっかけを与えました。
浜田さんは、医療分野から政治家へと転身した異色の経歴を持つ人物です。彼の活動は、NHK問題という一つのテーマに特化することで、多くの人々の共感を呼び、政治に新たな視点を持ち込んだと言えるでしょう。
そしてついに 総裁として 政治団体『日本自由党』の立ち上げが発表されました!
彼は必ず国政に還ってきます。
並の政治屋たちが震えて見て見ぬふりをする、この国の病状にまたメスを入れるために。

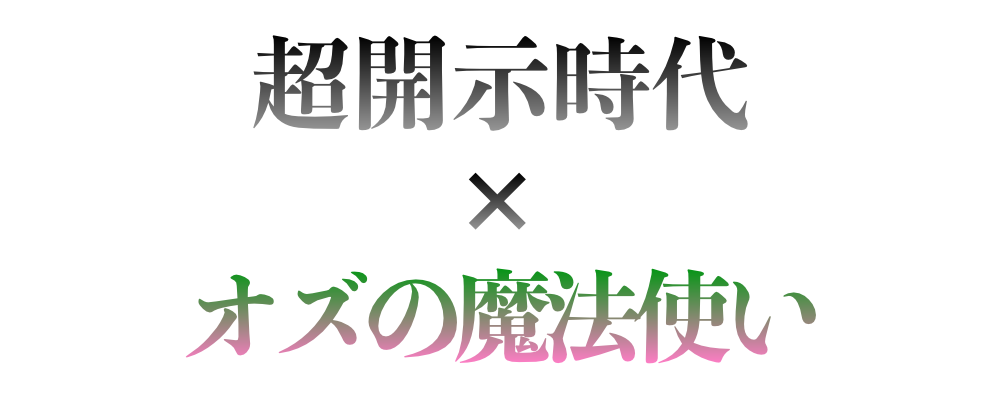

〜 “メディア”の世代交代 〜
メディア(media)とは?
情報の記録・伝達・保管などに用いられる物や装置のことである。
—
人々は長いあいだ、巨大な顔に語りかけられてきた。
轟く声、炎の演出、圧倒的な権威。
それが真実だと信じ、疑うことすら許されなかった。
しかしある日、ひとりの勇気ある者がカーテンを開いた。
そこにいたのは、機械仕掛けに隠れて震える小さな人間。
「オズの魔法使い」の正体は、権威の仮面を被ったただの存在にすぎなかった—————–。
この寓話をファンタジーとして笑い飛ばすのは簡単だ。
だが私たちが生きる現代こそ、その舞台に酷似してはいないだろうか。
オールドメディアという“魔法使い”🧙
戦後日本を覆ったオールドメディアは、まるで魔法使いのごとく国民を導き、時に恐怖を与えた。
編集会議で決められた“顔”を巨大スクリーンに映し出し、効果音と炎の演出で真実を装った。
その光景は、疑いを持たぬ大多数に「現実」として刷り込まれていった。
けれども、SNS時代がそのカーテンを開け放った。
“政治家”と名乗りながらときになんとなくの美辞麗句を並べ、時に大声で揚げ足取りしてれば年間数千万円と名誉を享受できる。
”新聞記者”と名乗りながら正体は単なる左翼活動家だった。記者会見で延々と自分の見解を述べ質問という形で押し付ける。
”TVアナウンサー”と言いながら選挙期間中に特定候補者を狙い撃つ。もっともな正義顔をして出る杭をまたしても打つのである。
結論ありきでそちらへ誘導し、失言を引き出してお得意の”上から成敗”を発動するのである。
それを口をポカーンと開けて「そうか、こいつは悪いヤツだ!」なんて直線的に信じるほど
大衆はすでに馬鹿じゃないだろう。
アップデートできぬ オールド政治屋 / オールドメディア / オールド大衆 が
いつまでも戦後の同じスタイルでそれっぽいことをしながら何も変えられず
駅前ロータリーをぐるぐる回り続けて今日の停滞感を招いてきた。
個人がメディアになる時代📢
ツイートひとつが、ライブ配信ひとつが、仮面を剥ぎ取る。
議事録は隠せない。密室のやりとりは、瞬く間に光の下にさらされる。
政治家の言葉は編集を飛び越え、ダイレクトに民意へ届く。
かつてブラックボックスに閉ざされていた政治の内情は、
新しい世代の政治家たちの手によって次々とオープン化されていく。
悪質なデマは全方位から分析解釈され、その稚拙さと愚かさを
特大ブーメランとしてデマ発信者に返すようになってきた。
混乱と希望のあいだ
それは混乱でもある。
誰もが発信者となるこの時代は、真偽が交錯し、情報の洪水を生んでいる。
だが同時に、それは希望でもある。
一人ひとりがメディアとなり、虚構の仮面を暴く力を持った。
そしてその「一人ひとり」には、あなたも含まれている。
あなたが善意を持って声をあげるとき、
その小さな発信はカーテンをさらに開き、誰かを照らす光になる。
嘆くだけではなく、真実を示し、勇気を与える言葉を発すること。
それこそが、この時代を生きる者に与えられた特権であり、責任なのだ。
“メディア”の世代交代 📱
私たちは、超開示時代に立っている。
権威が剥がれ落ち、素顔がむき出しになる時代。
カーテンの向こうに何があるのか——
それを見極め、照らし出すのは、我々ひとりひとりでもある。
あなたもメディアなのだ。虹を超えていこう。


日本史上最もアツい国防戦争 🔥
元寇は13世紀に世界最強のモンゴル帝国が日本を2回も攻めてきた超ガチな戦争。日本の武士たちが団結して撃退したレジェンド級の防衛戦。台風のアシストもあって勝利したけど戦費で鎌倉幕府は破産寸前に💸
🎯 元寇(げんこう)とは?
1274年と1281年にモンゴル帝国(元朝)が日本に仕掛けた史上最大規模の侵攻戦争。
- 別名:蒙古襲来(もうこしゅうらい)
- 規模:第1回約3万人、第2回約10万人の大軍
- 場所:主に北九州(博多湾)が戦場
- 結果:日本の完全勝利 🏆
🔥 なぜ戦争が起きたのか?
Step 1: モンゴル帝国の快進撃
- チンギス・ハンから始まったモンゴル帝国が世界を席巻
- 孫のフビライ・ハンが中国を支配し「元」を建国
- 朝鮮半島も制圧済み
Step 2: 日本への「上納しろ」要求
- フビライ「日本も俺らに従えよ😎」
- 鎌倉幕府の北条時宗「は?断る😤」
- フビライ「マジか…なら力で分からせてやる💢」
Step 3: 戦争準備開始
- 高麗に命令「船作れ、兵士出せ」
- 日本侵攻の大作戦スタート
⚔️ 2度の激戦
[第1ラウンド] 文永の役(1274年)
🔹 基本スペック
- 元軍: 約3万人(モンゴル+高麗連合)
- 日本軍: 約6,000人の武士
- 戦場: 対馬→壱岐→博多湾
🔹 戦闘の見どころ
- 元軍の新兵器: 火薬を使った爆弾「てつはう」登場。(漢字では”鉄砲”だが手榴弾に近い)
- 戦術の違い:
- 元軍:集団戦法、弓矢の雨
- 日本軍:一騎打ちスタイル(古すぎて苦戦😅)
- 決定打: 突然の台風で元軍の船が大破💨
- 結果: 元軍撤退 → 日本勝利
🔹 日本側の反応 「これはヤバい また来るでしょ…」→ 本気の準備開始
[第2ラウンド] 弘安の役(1281年)
🔹 パワーアップした両軍
- 元軍: 約10万人(モンゴル+高麗+旧南宋の最強連合軍)
- 日本軍: 全国の武士が博多湾に集結
- 新要素: 日本が 元寇防塁(高さ2mの石の壁)を建設済み
🔹 戦闘の展開
- 元軍「前回の石垣邪魔すぎ…上陸できん」
- 日本軍「今度は準備万端だぞ😤」
- 海上での激しい攻防戦が約2ヶ月継続
🔹 再び神風降臨
- またもや台風が直撃🌪️
- 元軍の船団が壊滅状態
- 生き残った兵士も捕虜or討死
- 完全勝利達成 ✨
📊 元寇の影響度
ポジティブ効果
- 武士の団結力UP: 「俺たち強え」という自信獲得
- 技術革新: 火薬兵器の存在を知って軍事技術向上
- 神国思想: 「日本は神様に守られてる」という特別感
- 防衛意識: 海外の脅威を意識するように
ネガティブ効果
- 財政破綻寸前: 戦費と恩賞で幕府の金庫が空っぽ
- 武士の不満: 「頑張ったのに報酬少なすぎ」
- 重税: 民衆への負担増加
- 幕府衰退の引き金: 結果的に鎌倉幕府滅亡の遠因に
🌟 なぜこの戦争がレジェンドなのか
世界史的インパクト
- モンゴル帝国初の大敗北: ユーラシア大陸を制覇した最強軍団が初めて完敗
- 海戦の先駆け: 大規模な海上侵攻作戦として軍事史に刻まれる
- 東西文化の激突: 全く異なる戦術と文化の正面衝突
日本史的インパクト
- 初の国家総力戦: 日本全体が一つになって戦った初体験
- 武士道の確立: 命を懸けて国を守る精神的支柱が形成
- アイデンティティ形成: 「日本人」としての意識が芽生える
🎬 元寇を描いたエンタメ作品たち
🎮 ゲーム
『Ghost of Tsushima』(2020年)PS4/5
- 元寇の対馬を舞台に、境井仁が蒙古軍と戦うオープンワールド時代劇
- 海外開発ながら日本の美学を完璧再現した美麗なビジュアル
描かれる自然や文化はため息が出るほどに美しい - 映画級のクオリティで侍体験ができる傑作
- 対馬島は聖地として観光地化🔗
- 10月に続編「Ghost Of Yotei」🔗 発売 →北海道の羊蹄山が舞台となる

📺 アニメ・漫画
『アンゴルモア 元寇合戦記』
- 対馬に送られた鎌倉武士・朽井迅三郎が蒙古軍と戦う本格歴史大河ロマン
- たかぎ七彦氏による文永の役での対馬の戦いを描いた作品
- 罪人武士の視点から描く生々しい戦闘描写
- アニメ版: 2018年放送、Prime Videoやdアニメストアで配信中
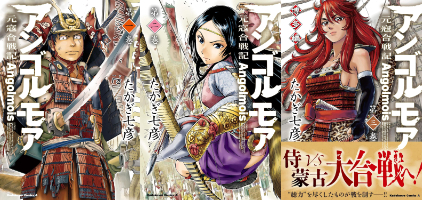
その他の関連作品
🎬 映画・ドラマ
- 『日蓮と蒙古大襲来』などの時代劇映画
- 『北条時宗』(NHK大河 2001)
- 『鎌倉殿の13人』(NHK大河 2022)
🏛️ リアル聖地巡礼スポット
対馬島 🌊
- 『Ghost of Tsushima』の聖地として観光地化
- 小茂田浜: 実際にモンゴル軍が上陸した歴史的海岸
- 元寇関連史跡が多数現存
福岡・博多 🏯
- 元寇防塁の遺跡: 高さ2mの石垣が一部現存
- 博多湾: 第二次侵攻の主戦場
- 各神社: 元寇関連の祭神を祀る
🔥 まとめ: なぜ今でもアツいのか
元寇は単なる昔の戦争じゃない。
- 絶望的状況での大逆転劇 📈
- チームワークの力を証明 🤝
- 運も味方につけた完璧な勝利 🎯
- その後の日本を決定づけた転換点 🔄
世界最強の敵に立ち向かい、準備と団結力、そして少しの運で勝利を掴んだ。
まさに 歴史上最もアツい国防戦争 と言えるでしょう。
現代でも「ピンチをチャンスに変える」「チーム一丸となって困難に立ち向かう」というメッセージは色あせることがありません。元寇は、日本人の「負けない心」の原点なのかもしれませんね 💪
P.S. 台風のタイミングが神すぎて、本当に「神風」って呼ばれるのも納得です🌪️

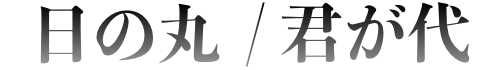
🇯🇵誇り高き 国旗・国歌
「日の丸」と「君が代」。学校の式典で何度も見聞きしたことがあるけれど、基礎的すぎるがゆえに実際のところどんな歴史?なぜこのデザイン?そんな疑問を持ったことはありませんか?その成り立ちから現在までをわかりやすく解説します。
🇯🇵日の丸 ~世界一ミニマルな国旗の秘密~
どうやって生まれたの?
日の丸の歴史は意外と古く平安時代まで遡ります。当時の武士たちが戦いの時に「太陽の力で勝利を!」という願いを込めて、扇や旗に太陽を描いていたのが始まり。自然信仰からくる価値観で”力の源”として掲げたのでしょう。
日本神話に登場する最も重要な神の一柱であり、太陽を神格化した存在が 天照大御神 です。皇室の祖神=ご先祖ともされており、日本一の神社である伊勢神宮に祀られています。
昔聖徳太子が外交上の戦略で、地理的に東から昇る太陽になぞらえ”日出ずる国”と称したことも大きなきっかけでしょう。EXILEも歌った”ライジング・サン”です。
時は流れ江戸時代になると、海外貿易で活躍する日本の船の目印として使われるように。そして明治時代の1870年、ついに正式な日本の旗として採用されました。私たちがよく知る法的な国旗としては、1999年に「国旗国歌法」で決まりました。どこかで瞬間的にデザインされたのではなくとても長い年月を経て定着したイメージと言えるでしょう。
特徴
良いところ
- 超わかりやすい:遠くからでも「日本だ!」ってすぐ分かる
- 誰でも描ける:誰でも簡単に描ける超ミニマルデザイン
- 意味が深い:白は「純粋さ」、赤は「太陽のエネルギー」を表現
ちょっと困るところ
- 歴史的な複雑さ:戦争の記憶と結びつけて見る人も一部いる
他の国と比べてみると?
アメリカの星条旗🇺🇸は50個の星と13本のストライプで州の数を表現、イギリスのユニオンジャック🇬🇧は3つの国の旗を組み合わせたデザイン。モザンビークの国旗🇲🇿は当時軍事支援したソ連の武器 AK-47(アサルトライフル!) が使われています。さらに他の国では動物がいたりまるで企業ロゴみたいに千差万別です。
それに対して日の丸🇯🇵 は太陽という、誰にでも分かる自然のシンボルを
世界有数の歴史を持つ国としての先行者益?としてありがたく使わせていただいております。
雲ひとつなき快晴の空にはためく日の丸はとても美しいです。
素晴らしい国旗で誇りに思います。
🇯🇵 君が代 ~1000年の歴史を持つ国歌~
歌詞
君が代の歌詞、実は1000年以上前の和歌が元になってるんです。平安時代の『古今和歌集』(905年)に収録された短歌がベース。なんと作者は「読人知らず」=作者不詳。もともとは恋人や友人の幸せを願う歌だったんです。
世界的に見ても珍しい、悠久の流れを感じさせる1000年の歴史を持つ歌詞です。
そして明治時代に国歌が必要になった時、この古い歌詞にメロディーをつけたのが始まりです。
曲に関しては最初はイギリス人が作曲しましたが、その後ドイツ人音楽家が今の荘厳な旋律に作り直しました。純日本でないのは意外ですね。
お祝いの歌
この歌は『古今和歌集』の「賀歌」部に分類されており、祝賀の歌として、主に長寿や幸福を願う内容です。具体的には、天皇ではなく、個人への誕生祝いが多く、例として本康親王や藤原定国への祝福が含まれます。つまり、「君が代」の原歌は、親しい人へのバースデーソングとして始まりました。
「きみ」の語源に関する諸説
「きみ」は、男女を表す「き」と「み」に由来する説があります。「き」は男性、「み」は女性を指し、これにより「きみ」は人間全般や愛する人を表すことに。この説では、「君が代」は特定の支配者ではなく、愛する人への祝福の歌となります。古典文学における「君」は、時代によって異なり、最初は親族や友人、配偶者などを指し、必ずしも天皇ではありませんでした。しかし、院政期以降、天皇を指す場合が増えました。
音楽
君が代の曲には実は2つのバージョンがある
1回目(1870年):イギリス人が作った版
最初はイギリス陸軍の軍楽隊長フェントンが作曲しました。でもこの曲、日本人には全然合わなかったんです。なので「この曲、変えない?」という意見が出て、結局ボツになりました。
2回目(1880年):日本人が作った現在の版
今の君が代は明治時代の日本人音楽家が作り直したものです。これが現在まで使われています。
「雅楽」っぽい音階を使っている
雅楽って何?→ 日本の宮廷音楽のこと。お寺や神社で聞く、あの独特な音楽です。君が代は「ドレファソラ」の5つの音だけを使って作られています。普通の歌は「ドレミファソラシド」の7つの音を使うのに、君が代は5つだけ。これが日本っぽい響きになる理由です
でも伴奏は西洋風
面白いのは、メロディーは日本風なのに、伴奏(ハーモニー)は西洋音楽のスタイルになってること。ドイツ人の音楽家エッケルトが伴奏をつけたからです。
つまり:
- 歌のメロディー = 日本風(雅楽っぽい)
- 楽器の伴奏 = 西洋風(ピアノやオーケストラっぽい)
君が代って他の国の国歌と比べて異常にゆっくりですよね。一つ一つの音をじっくり歌います。
また本当は前奏はないんですが、みんなで歌い出しを合わせるために「君が代は〜」の部分を最初に演奏することが多いです。
まとめ
- 日本の伝統音楽と西洋音楽を混ぜた珍しいハイブリッドスタイル
- 5つの音だけで作られているから独特な響き
- すごくゆっくりで荘厳な感じ
これが君が代の音楽面が他国の国歌と全然違う理由なんです。
世界の国歌と比較すると?
フランス🇫🇷の「ラ・マルセイエーズ」は革命の戦いを歌った勇ましい曲ではありますが
『血まみれの旗が掲げられた 聞こえるか 戦場の残忍な敵兵の咆哮を?
奴らは汝らの元に来て汝らの子と妻の 喉を掻き切る!』という凄まじさ。
Wカップなどの舞台でも胸に手を当てて歌っているわけです(笑)
アメリカ🇺🇸の「星条旗」も戦争での勝利を称える内容で「ロケットの赤い光が、空中で破裂する爆弾が」「彼等の邪悪な足跡は彼等自らの血で贖われたのだ」ときます。それでも1991年スーパーボウルでの故ホイットニー・ヒューストンの国歌”絶唱”はこれまで見たメジャー舞台での斉唱で最も素晴らしいものだったと思います。
ロシア🇷🇺国歌は元々 前身のソビエト連邦(ソ連)崩壊で新しい国歌にいったんは変わったのにプーチンが政権を取ってからわざわざ復活させたものです。確かに勇壮なメロディーは曲として素晴らしいです。歌詞については元々『偉大なレーニンは道を照らした スターリンは我々を育てた』と指導者/独裁者の個人名が入っていたのが時代的でしたが、ロシア国歌として復活させる際にはなんと同じ作詞者に新しい歌詞を再度依頼したというエピソードもあります。プーチンのソ連をベースにした価値観かもしれません。
そして我が日本。他国のアドレナリン大放出的な”動”イメージに比較するとあまりに穏やかな”静”イメージ。解釈がどうのこうのと曲解含めて色々言われてますが、「君が代」には戦いや革命のワードはなく「永遠の平和と繁栄を願う」というメッセージ。これも長き歴史を経てきた日本国らしい平和志向の表れと言えるでしょう。
まとめ:私たちはどう向き合うべきか
先日こんなランキングが発表されていました。
もちろん独断/偏見要素もあるでしょうが これは誇らしいものです。
日の丸と君が代、どちらも
- シンプルで美しい:無駄のない洗練されたデザインと音楽
- 深い歴史:1000年以上の長い歴史を持つ日本文化の結晶
- 議論の対象:歴史的経緯から様々な見方がある
大切なのは、まず「知ること」から始めること。その上で、一人ひとりがどう感じるか、どう次の世代に伝えていくかを考えていけばいいのではないでしょうか。
ただ 時折見られる、日の丸にバツをつけたり踏んだり火をつけたりという国内外での行為や、一部教師による君が代斉唱の拒否パフォーマンスなどは理解できません。海外では当たり前の”国旗損壊罪”の一刻も早い施行が待たれるところです。国家軽視へ誘導したいという意図する連中にこういう細部の欠落を悪用させてはいけないと思います。
改めて 日本国の 国旗たる”日の丸”、国歌たる”君が代” ともに素晴らしいです。
この祖国に生まれ生きていく
以上、誇り高き国の象徴としてしっかりと抱いていきたいものです。


[ Podcast ]
音声プレイヤー
[ Editor’s Note ]
vol.1いかがでしたでしょうか。
政治、セイジ。ポリティクス。
いくら無関心でも無関係でいられないものです。
放置しておくと 稼いだお金を不可解な税金や社会保険料でごっそり持っていかれたり、治安が悪くなったり、他国侵略のお膳立てを秘密裏に進められたりします。
今日と同じ当たり前の日々が 当たり前に続いていく保証はありません。
本来 政治家 とは 私達が生活改善への願いを託し、改善し立法し実践してもらうための精鋭たち。
そして私たちは税金で彼らを雇う”雇用主”側です。
期待以上の大剣をふるって国をアップグレードしてくれる政治家もいれば、試験も資格もなく選挙期間だけ美辞麗句を並べ大声パフォーマンスしただけでその立場を入手したりする人間も少なくありません。
そういう残念な政治屋たちには サイレントマジョリティーの無関心はよだれの出るご馳走です。
節約したり副業やったりするよりも、不明瞭な支援金、ムダ遣い、キックバックで私腹を肥やすような政治家を”選ばない”ために普段からアンテナは張っておきたいと思います。
長く続く連続ドラマやコミックを途中から見始めるように、最初は点だったものが次の点とつながり、いつしか線になっていくほど面白くなっていきます。推しのプレイヤーや政党もできていくでしょう。
映画「マトリックス」で栄養を吸収されるプラグを首に刺されたまま夢を見て収穫のために”栽培”されていた人たちのようにならぬよう、無関心や思考停止のプラグを抜きましょう。
「 Unwire = ワイヤー(線)を外す、切る、ほどく 」
情報の束縛、社会的同調圧力、無意識の習慣、構造そのものから自由になる というニュアンスがあります。
小規模の不定期刊行ですがinstagramでリリースインフォは出していく予定です。
vol.2もぜひ見に来ていただければと思います。
それではまた!

本サイトは現在広告を使用しておりませんので
応援サポートをいただければ幸いです